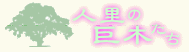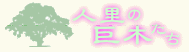|
 |
|
名称 永福寺のスギ (えいふくじのすぎ)
名称の典拠 なし
樹種 スギ
樹高 34m(注1)
目通り幹囲 5.3m(注2)
推定樹齢 不明
所在地の地名 長野県塩尻市塩尻町
〃 3次メッシュコード 5437−17−18
〃 緯度・経度 北緯36度06分05.6秒
東経137度58分56.4秒
天然記念物指定 なし
撮影年月日 2024年10月17日
注1)環境省巨樹データベース(1998年調査値)による
注2)まったくの目分量
小坂田の池を間に挟んで、高台の道の駅「小坂田公園」の南西約500m。かつての中山道塩尻宿の東に、高野山真言宗慈眼山永福寺がある。
境内東側に万延元年(1860)建立の観音堂(市指定文化財)があり、馬頭観音が安置されている。
永福寺に伝わる縁起によれば、この馬頭観音は今から千数百年前、「岡の屋の牧」という御料馬の産地長者原に祀られたことに始まる。
のち大永元年(1521)、木曽義仲の子孫義方がこの馬頭観音を本尊として長畝の福沢に臨済宗長福寺を開山。江戸時代に入って塩尻宿が開かれると、寺を宿場近くに移動、宗派を真言宗に変え、また当時の将軍吉宗の嫡男の名が長福丸であったので、同名を憚って寺号を永福寺と改めた。
明治初めの混乱期には、役所になったり学校になったりしたこともあったようだ。(「少し大きめの画像」に案内板の画像を掲載したので、詳しくはそちらを)
仁王門を潜った先、右手に左図のスギが立つ。いわゆるオモテスギのタイプだ。
本堂からも近い位置に立つのだが、幹に注連縄を付けている。
それは永福寺に限ったことではない。明治初期のようには神仏を厳格に区別せず、再び寛容な時代にもどったということなのだろう。
環境省データでは幹囲489cmとされているが、それから25年以上を経て、今は5mを超えていると思われる。 |
|