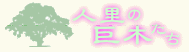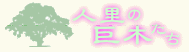|
 |
|
名称 来尾の桂 (きたおのかつら)
名称の典拠 「浜田市の名木」指定名称を参考(注1)
樹種 カツラ
樹高 13m(注2)
目通り幹囲 8m(注3)
推定樹齢 不明
所在地の地名 島根県浜田市旭町中来尾
〃 3次メッシュコード 5232−12−66
〃 緯度・経度 北緯34度48分23.9秒
東経132度19分53.8秒
天然記念物指定 なし
撮影年月日 2024年10月11日
注1)浜田市の名木としての名称は「来尾の桂(金屋子神木)」だが、私のサイトでは括弧内を省略させてもらった
注2)標柱側面に記されたデータによる
注3)株全体の輪郭を目分量で。8mに達しないことはあるまいと思ったので…
浜田市と広島県安芸太田町を結ぶ県道が11号(旭戸河内線。県道番号や名称は両県で共通)である。
県境の峠が来尾峠。交通量が少ないのか、峠付近では舗装はされているものの、一車線県道で、冬期は通行止めとなる。
峠から九十九折りを下り、来尾川の谷の上部、中来尾の集落に入ると、右手下方、川の近くにカツラの大きな樹冠が見えてくる。
株立ちのカツラである。来尾川左岸の川岸に立ち、根は水面下まで届いていると思われる。
周囲が開けており、また、カツラのすぐ下流に橋が架かっているので、対岸から眺めるも可。
このカツラは「金屋子神木」とも呼ばれているようだ。
私の乏しい知識で説明すると、金屋子神(かなやごのかみ)は、製鉄や鍛冶に関わる神である。特にここ中国地方では鑪(たたら)製鉄と結びついていることが多いように思われる。
そして、このカツラのみの話ではなく、何故かカツラの木が金屋子神の神木とされるようなのだ。
私の盆暗頭では、製鉄・鍛冶と樹木の関係について、「薪」くらいしか思いつかないのだが、それが何故、ほかの樹種でなくカツラでなければならないのだろう。カツラの木は特に火力が強いのだろうか?
それとも何か神話的な意味があるのだろうか?
ここから先は私の理解が及ばない。どうかご自分でお調べを。 |
|