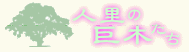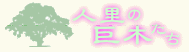|
 |
|
名称 光超寺の大イチョウ (こうちょうじのおおいちょう)
名称の典拠 現地の案内表示
樹種 イチョウ
樹高 17m(注1)
目通り幹囲 4.8m(注1)
推定樹齢 400年(注1)
所在地の地名 島根県浜田市金城町小国(おぐに)(柚根(ゆね))(注2)
〃 3次メッシュコード 5232−11−88
〃 緯度・経度 北緯34度49分14.1秒
東経132度13分21.6秒
浜田市指定天然記念物(1993年3月31日に合併前の金城町が天然記念物指定した町内20ヶ所に散在する樹木を、「金城町の巨樹・銘木」の名称で一括指定)
撮影年月日 2024年10月11日
注1)島根県公式ウェブサイト中のPDF版「島根県の巨樹・巨木」による
注2)2005年10月1日、浜田市に合併。旧行政区は那賀郡金城町(かなぎちょう)
浜田自動車道金城スマート・インターチェンジの近くから県道114号(今福芸北線)を南下、小さい峠をいくつか越えて、小国川の谷に出たら東へ。そこから1kmほど走ると小さな盆地に出る。視界が開けたところで、東の山裾、小高い位置にイチョウの大きな樹冠が見える。それが浄土真宗本願寺派大舊(旧)山光超寺境内に立つこのイチョウである。
上記「島根県の巨樹・巨木」によると、『防火の願いを込めて』植えられたとある。
イチョウに乳授け信仰があるように、防火信仰もあるのかと誤解されそうだが、そうではない。
今もそうだが、住宅火災にしろ山林火災にしろ、大火にしないためには、延焼を食い止めることが何より求められる。
昔の建物の屋根は、殆どが萱や藁、木の板等、可燃性の素材で覆われていた。だから、火の粉が飛んできて、屋根に落ちると、そこから火が広がる。いわゆる「飛び火」である。
そういう状況にあって、イチョウは、屋根よりも高く聳え、水分を多く含み容易に燃えない葉を大量につける。だから、風に乗って飛んでくる火の粉を防ぐ防火壁としてとても優秀だったようだ。
社寺にイチョウが植えられたのは信仰のためではなく、実用性があったのである。
この光超寺でも、明治38年の火災で延焼を防いだと伝えられているらしい。(注3)
なお、まったく話は変わるが、当地金城町小国は、劇作家島村抱月(しまむらほうげつ、1871〜1918)の出生地である。「抱月ふるさと公園」など、町内のあちらこちらに抱月の名前を見ることができる。
抱月の実父は、晩年を光超寺の隣の家で過ごしたそうである。
注3)「島根県の巨樹・巨木」による。実際はそうでもなかったようだが…。詳細については「少し大きめの画像」に載せた案内板をお読みいただきたい |
|